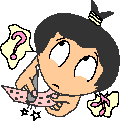
オルゴール編曲講座(第四回)
|
|
オルゴール編曲講座(第四回) |
この講座も4回目になりました。 オルゴール しかも20個しか音がないこのオルゴールでどこまでやれるのか あまりふりかぶった感覚はありませんが 結構おもしろいテーマだと思っています。 オルゴールという機械の性格なども知った上でないとなかなか満足いく編曲って出来ないものですね。 ただこのホームページでも度々紹介しているように このオルゴールの音階は実に“絵画的”なんですね。 適当に音をおいていっても あら不思議!? 結構いい曲?になっているではありませんか。 てなわけでお気楽に行きましょう。
【連続音?? なんでしょうこれって...】
連続音とは オルゴールが最も苦手とするもので 同じ音が短い間隔であらわれることです。 ピアノなど他の楽器ではテンポ感、躍動感などを演出するのに多用されますよね。 しかしオルゴールでは鋼鉄の弁をピーンと弾いて音を出し、しかもその音を止める機構もない訳ですから その振動がある程度おさまってからでないと弾けないですよね。 実際にはダンパーと言われる機構が弁についてましてある程度なら振動中に次の弾きをしても前の振動をソフトに止めてくれるのであまり心配はないんですが とにかく余り短い間隔で演奏する(弾く)とノイズが目立ってあまり美しくないのです。
それにカード式オルゴールではスターホイールという爪のついた円板を回して弁を弾いています。→こちら
ですから爪の間隔(約7mm)以下に配置された穴があっても後ろ側の音が出ないのです。(爪が回ってこないからしかたがない)
そんなこんなで連続音は無理とあきらめて それを逃げる方法を考えるのが妥当だという訳です。 実はこれが厳しいのでして、私に言わせると半音なんかなくても連続音が使えない方がずっと厳しいと感じるほどです。相当に原曲のイメージを損ねることになりやすいのです。
ちなみに大型のオルゴールですと同じ(くらいの)音程に調律された複数の弁を用意しておいて交互に使うことで連続で同じ音が出せるようにしたものが多いです。(うらやましい....)
これまでも何度も言いましたがこれはあくまで私の私見ですので一般論ではありません。
【実際にどんな風に処理しましょう】
まずは一曲聴いてみてください。 昨年2002年のクリスマス時期にアップしたTwelve
Days Of
Christmas(イギリス民謡)です。 お手持ちのMidiプレイヤーで結構です。(ただクリックすれば再生されると思います。)
どこが連続音を処理した結果か判りますか? そう各フレーズ(メロディの単位)の出だしの所ですね。 原曲に近いイメージ(それでもだいぶ編曲して変えてますが)の曲と比べてみてください。
そう たったこれだけのことができないんですね。 結構情けないでしょう。 でもこれを逃げられないとオルゴールにできる曲レパートリーが一気に小さくなってしまいますね。 がんばって工夫しましょう。
このケースでは カードにする際の小節当たりの長さ(mm)を大きくすれば理論的には回避できるはずです。 でも その場合はカードが異常に長くなってしまい、結果的には手回しを超人的なスピードにしないといけなくなってしまいますね。 いっそ電気モーターでターボ全開!なんて感じにしないと... これでは現実的ではないのでどうしても連続音のまま置いておくことはできない訳です。
そこで事例の通りの編曲になった訳です。 ここでのミソはタタタン タタタンというリズム感を残すようにしてまん中の音だけオクターブ下げて逃げたわけです。
これはワーグナーの歌劇タンホイザーからの出典ですが いわゆるファンファーレですね。 威勢のいいこの出だしのフレーズ これはオクターブ下げたり上げたり程度では納まりがつきませんね。 この場合は威勢の良さを最大に生かす意味で オルゴールで最大の威勢の良さを誇る????下降フレーズを だんだん厚くして(音を重ねていくこと)いきながら盛り上げていこうという訳です。 これは連続音の処理としては高度な部類?かもしれませんね。 でも楽しいでしょ? こういったことこそ編曲の醍醐味かもしれません。 なんて知った風なこと言ってしまいました。
ただ 予めお断りしておきますが 編曲が不可能 または編曲しても極めて不自然なものになる可能性もありますよ。 さらに移調もハ長調に...とは限りませんのでいろいろ考えてみてください。 筆者もまだ何も考えていません。(無責任...)