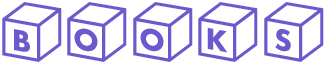 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| よしんば君がうんざりするような文章に出くわすとしても、それは決して、君を顛覆させるための暗礁として僕がそこに置いたのではなく、君が僕の通ったあとを認めることができるように、浮標として、置いたものなのだ。
Le Potomak/Jean Cocteau |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自分から本を読むということを取ってしまったら、この経験の無い私は、泣きべそをかくことだろう。それほど私は、本に書かれてある事に頼っている。一つの本を読んでは、パッとその本に夢中になり、信頼し、同化し、共鳴し、それに生活をくっつけてみるのだ。また、他の本を読むと、たちまち、クルッとかわって、すましている。人のものを盗んで来て自分のものにちゃんと作り直す才能は、そのずるさは、これは私の唯一の特技だ。本当に、このずるさ、いんちきには厭になる。毎日毎日、失敗に失敗を重ねて、あか恥ばかりかいていたら、少しは重厚になるかも知れない。けれども、そのような失敗にさえ、なんとか理屈をこじつけて、上手につくろい、ちゃんとしたような理論を編み出し、苦肉の芝居なんか得々とやりそうだ。(こんな言葉もどこかの本で読んだことがある)
女生徒/太宰治 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| わが夢を王冠に戴きながら
美が花咲いている前世の空に よみがえることを私は好む 窓/マラルメ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOOK
BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOOOOOOK! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| けれどもそれは明らかに私に向ってささやかれた言葉、たまゆらの、愛の告白でありました。
撲滅の賦/澁澤龍彦 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日はうららかに川面を射て、八畳の座敷は燃えるように照った。川面から反射する光線が、無心に眠る娘の顔や、障子の紙に金色の波紋を描いてふるえていた。
刺青/谷崎潤一郎 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOOK! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| そのくらいの不幸、あったほうがちょうどいいよー。
るきさん/高野文子 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| おわかれ致します。あなたは、嘘ばかりついていました。私にも、いけない所が、あるのかも知れません。けれども、私は、私のどこが、いけないのか、わからないの。
きりぎりす/太宰治 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「自分は淋しさをやっとたえて来た。今後なお耐えなければならないのか、全く一人で。神よ助け給え」
友情/武者小路実篤 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| どちらにしても
私は たいへん 君を好きだったね 綿の国星/大島弓子 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治の男だから愛情の表現は下手だったが、遺言には「次の世でも私の妻になって下さい」と書いてあった。
東京の空の下オムレツのにおいは流れる/石井好子 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・BOOK? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| カフェやジャズによって代表される昭和初期の新風俗を描くのに、コクトーの機智にみちた、パンチの効いた、スピード感のある比喩は、まさに打ってつけだったといえよう。
偏愛的作家論/澁澤龍彦 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| いまハンスの考えと夢は、とっくに疎遠になっていたこの世界の中で動いていた。
車輪の下/ヘルマン・ヘッセ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BOOK
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| そんなお気に入りの喫茶店が店を閉めてから少しして、
恋人がぼくのもとから去ったので、 ぼくは「コーヒーと恋愛」の両方をほぼ同時になくしてしまったことになる。 昨日・今日・明日/曽我部恵一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| とつぜん、狂ったように、叫びだす。なんと言えばいいのか分らないので、意味のある言葉にはならない。ただ、声をかぎりに、ありったけの力でわめくのだ。そうすればこの悪夢がおどろいて目をさまし、思わぬ失態をわびながら、彼を砂の底から、はじき出してくれるとでもいうように。だが、出しつけない声は、いかにもかぼそく、弱々しかった。おまけに、途中で砂に吸われ、風に吹きちらされて、どこまでとどくものやらも心もとない。
砂の女/安部公房 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「じゃあ仕方ない、友達のキッスでもしておくれよ」
「大人しくしていればして上げるわ、だけども後で気が変になりやしなくって?」 「なってもいいよ、もうそんな事を構ってなんかいられないんだ」 痴人の愛/谷崎潤一郎 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜花は一本かニ本がよい。
そして、淡い夕闇の中で見るのが好きだ。 また、さらに、桜花は散りぎわがよい。 小説の散歩みち/池波正太郎 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| つい涙ぐんでいた。なんの涙かの説明はつけにくい。こんな信じ難い献身が、現実に存在していたことへの驚き。見るまでは信じられなかった、自分の卑俗さへの羞恥の念。自己放棄には心を絞って涙に変える作用があるのかもしれない。
カンガルーノート/安部公房 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持って生まれた美貌とか
技巧も手の届かない自然のままの 新鮮な顔色とかいった そうした自然の贈り物だけでは、 愛情が見つけ出した 目に見えないたった一つの魅力ほどには 人の心を動かすことは望めません。 捲き毛のリケ/Charles Perrault、訳・澁澤龍彦 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「こういう味のものが、丁度いま食べたかったんだ。それが何だかわからなくて、うろうろと落ちつかなかった。枇杷だったんだなあ」
〈略〉 どうということもない思い出なのに――。丁度食べたかったものを食べていたりすると。梅雨晴れの午後のその食卓に私は坐っています。 〈略〉 向い合って食べていた人は、見ることも聴くことも触ることも出来ない「物」となって消え失せ、私だけ残って食べ続けているのですが――納得がいかず、ふと、あたりを見まわしてしまう。 ひょっとしたらあのとき、枇杷を食べていたのだけれど、あの人の指と手も食べてしまったのかな。――そんな気がしてきます。夫がニ個食べ終るまでの間に、私は八個食べたのを覚えています。 ことばの食卓/文・武田百合子、画・野中ユリ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| あの人の不在はわたしの頭を水中に押し込む。少しずつ息がつまる。肺の中の空気が薄くなる。この窒息状態を通じてこそ、わたしはおのれの「真理」を再構築し、愛というものの「手に負えなさ」を準備するのである。
恋愛のディスクール・断章/Roland Barthes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||